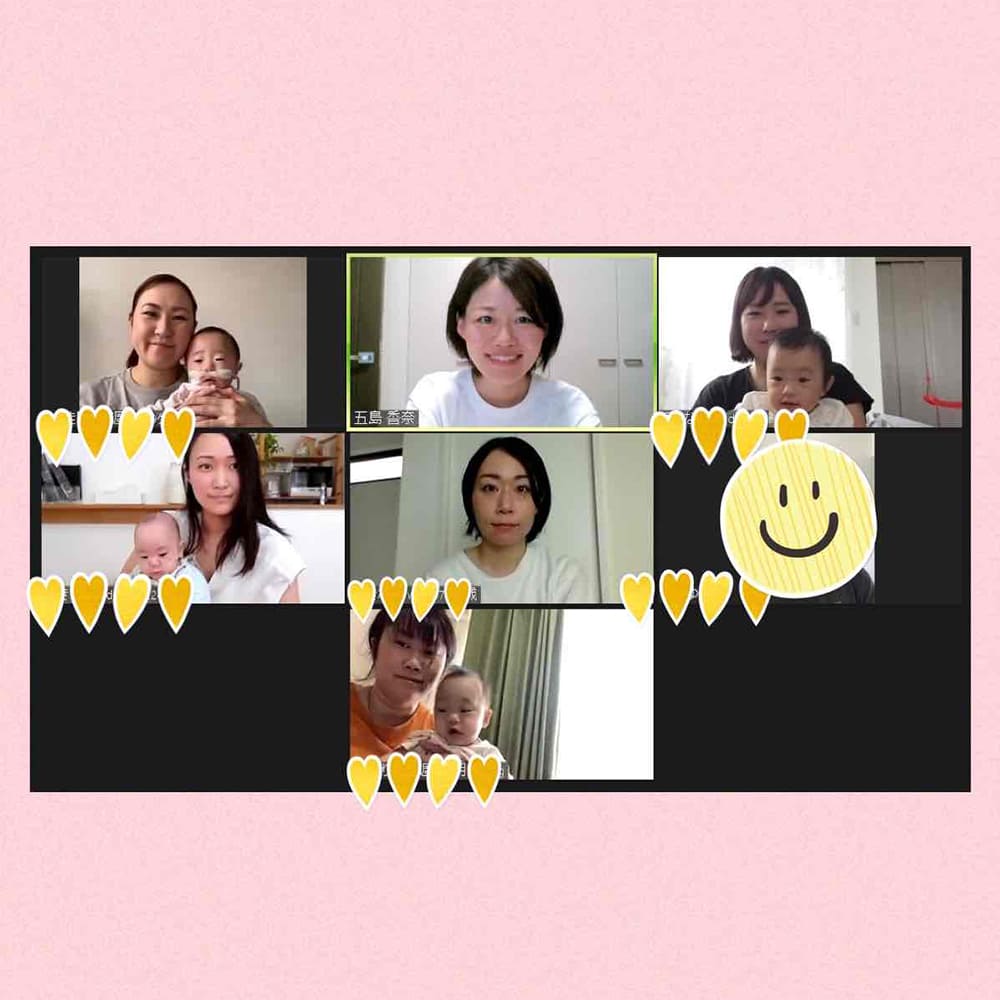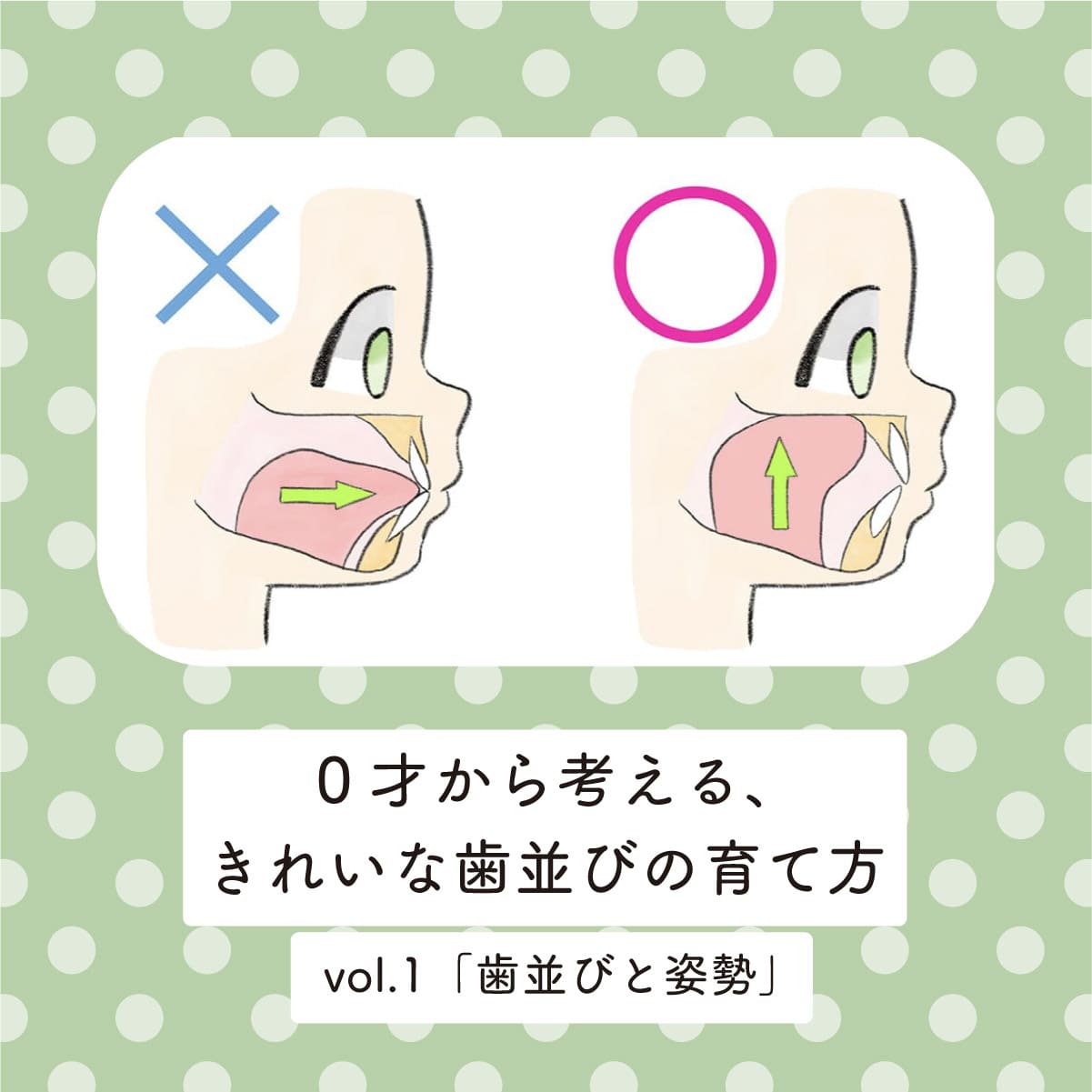周囲の協力を得ながら子育てをしていくにあたり、祖父母世代との関わり方や距離感に悩むパパママも多いと思います。
その悩みは、実は祖父母世代も同じように感じているかもしれません。過干渉になってしまう人、逆に遠慮しすぎてしまう人。「孫育て」における適度な距離感は、意外と難しいものです。
NPO法人「孫育て・ニッポン」の代表、ぼうだあきこさんにお話をお聞きしていくシリーズの第二回。今回は、祖父母との程よい距離感、世代間の違いを尊重しながら祖父母の経験を活かす方法などについてお聞きします。

《教えてくれた人》
NPO法人 孫育て・ニッポン 代表理事
ぼうだあきこさん
「NPO法人孫育て・ニッポン」理事長のほか、「NPO法人ファザーリング・ジャパン」理事、「一般社団法人産前産後ケア推進協会」監事、「3・3産後サポートプロジェクト」リーダーなど。産前・産後アドバイザー、防災士。
編集者としてのキャリアを持ち、育児雑誌や医療系の編集、育児サイトの立ち上げ・運営など、多岐にわたる分野で活躍。2011年に「NPO法人 孫育て・ニッポン」を設立し、子育てや孫育てに関する講座やプロジェクトを全国で展開し、家族間や地域社会での子育て支援の輪を広げるための啓発活動を行う。各自治体で配布されている「祖父母手帳」の制作も担う。著書に『祖父母に孫をあずける賢い100の方法』(岩崎書店)、2024年4月に発行したばかりの『娘が妊娠したら知りたい50のこと』(イースト・プレス)監修。
NPO法人 孫育て・ニッポン https://www.magosodate-nippon.org/
祖父母との付き合い方、距離感を考える
ーvol.1では、祖父母との世代間ギャップについてお聞きしました。世代間の「距離感」に悩んでいる人も多いと思います。
そうですね。パパママ世代は祖父母との付き合い方や距離感に悩んでいると思いますし、実は祖父母世代も、パパママ世代とどう距離感を取ればいいのか、悩んでいます。
これまでに支援をしてきたケースから一部お話しすると、娘を持つお母さんには、いろんなタイプの人がいて、「娘を囲い込み、過干渉になってしまう人」もいれば、「娘夫婦に対して過度に遠慮してしまう人」もいます。
過干渉なタイプの人には、とにかく程よい距離感と役割が大切です、と話します。
「子育ての主役はママとパパ。祖父母はサポーターなので、とにかく娘の話を聞きましょう、昔と今は違いますから…」と、世代による違いや、娘さん夫婦の子育てを尊重することの大切さをお伝えしています。
ただ、私たちがそうした発信に注力すればするほど、今度は「過度に遠慮してしまう」人も増えてしまうんです。
「かわいい孫のために何かしてあげたい」「頑張っている娘や息子を助けてあげたい」と思っていても、「今はあまり干渉しない方がいいみたいだから…」「昔とは時代が違うから…」と、距離を取り過ぎてしまうんですよね。
里帰りについても「パパの育休があるなら、私たちはもういらないわね」と、最初から距離を取ってしまうケースも多いです。
私は、昔と今とでは子育ての最新情報こそ変わりましたが、大事なところは変わっていないと思っています。
昔も今も変わらないのは、「周囲みんなで協力し合って、手をかけ目をかけ小さな命を育てていくこと」。
でも世間があまりにも「昔とは違う!」と過度に警鐘を鳴らすがゆえに、真面目な人ほど「子育てが変わってしまった、ゼロから学び直さなければ」「息子や娘にもっと配慮しなければ」と、どこか腫れ物に触るような関係性になってしまう。でもそれは、互いにとって理想の姿ではないかもしれません。
ー確かに、ほどよい距離感が大切ですし、初めての子育て、経験者である祖父母世代の助けは、とても大きいと感じています。
最近は、出産前のマタニティ教室に「祖父母教室」があったり、パパママと両方のご両親の計6人まで参加できる講座なども増えてきました。
そういう機会に私はいつも、赤ちゃん人形を持っていくんです。
そうするとお母様やお父様は、慣れた手つきで赤ちゃん人形を抱き上げ、とても優しい眼差しであやしたり、何も言わなくてもゆっくり揺れ始めたり、トントンと背を撫でたりするんです。
私たちはその姿を、新米ママやパパに見てほしいなと思っています。
お母様やお父様は、体が勝手に揺れてしまうほどに育児に精通した「経験者」であることを、その表情と行動が物語っています。
ママやパパたちには、「こういうところを真似てみるといいよ」とお話ししています。
また、こうしたマタニティ教室などでは、ママやパパに「新生児を育てたことがある経験者に、ぜひ入ってもらいましょう」と伝えています。
はじめての育児に奮闘するママやパパは、大袈裟にいってしまえば無免許運転で高速道路を走るようなもの。ベテランドライバーに、助手席に座ってもらうだけで、安心して運転ができます。
程よくアドバイスをもらいながら「みんなで一緒に」「助け合いながら」目的地を目指すことが大事だと思っています。

地域全体で、子どもを見守り育てていく大切さ
ー先ほど、過度に距離をとってしまう人もいる、というお話もありましたが、祖父母世代にとっては孫の誕生に対して、緊張や戸惑いのようなものもあるのでしょうか。
昔は子どもたちが近所の公園や空き地でのびのびと遊び、その様子を地域の大人たちが見守るという光景が当たり前でした。
自然な形でシニア世代が定期的に子どもたちと関わることで、その時々の子育ての空気感を少しずつアップデートしながら、地域全体で子育てを支えていたんです。
しかし、現代では共働き世帯が増え、子どもたちは保育園や学校や塾に通うため、日中に外で遊ぶ機会が減っています。
さらにコロナ禍で人と人との交流が減少したこともあり、今の祖父母世代は「もう何年も子どもと接していない」「子どもとの接し方がわからない」と感じる人が増えているのが現状です。
自分たちの子育てのころから、ぽっかりと間があいて、何十年ぶりに小さな子どもと接することになるのが、「孫の誕生」なのです。
自然と子どもに関わる機会が減ったため、情報がアップデートされずにいると、育児の方法も、昔のまま止まってしまいます。
こうしたギャップが、孫育てにおける摩擦を生む原因の一つになってしまうのかもしれません。
私たちの団体では「たまご育て」という考え方も提唱しています。
「他人の孫」を「たまご(他孫)」と呼び、たとえば地域の子ども=たまごたちを、少し気にかけながらみんなで見守っていきましょう、という呼びかけです。
自分の孫だけではなく、「たまご育て」を通して地域全体で子どもと関わり見守ること、シニア世代が地域の子どもたちと関わりを持つことで、子どもたちは多様な大人と接する機会を得ることができると思いますし、昔のように、シニア世代の情報のアップデートにもつながると思っています。
祖父母とのかかわり合いは「365日のうち、何日?」
ーパパママ世代からは、祖父母との関わりについて、どのような相談がありますか。
パパママ世代からは「孫に甘い」「ジュースやお菓子を与えすぎ」とか、「伝えたことを守ってくれない」「洋服やおもちゃを送ってくるのをやめてほしい」など、祖父母世代への不満をお聞きすることはやはりあります。
「夫婦で子育てのルールを決めているのに、それが崩されてしまう」という危機感があるのだと思います。
そんなとき、私は「我が子が祖父母と一緒にいる時間は、365日中、何日ですか?」と聞いてみます。
例えば、同居の人であれば365日/365日。この場合は、しっかりとルール作った方がいいです。毎日のことなので、子どもの健康や生活面に影響が出てくる可能性があります。
対して、遠方に住んでいる場合。会うのはお盆とお正月くらいで、おもちゃや服を送ってくる日を入れても、5日/365日とか、10日/365日もいかないくらいでしょう。
その数字が明らかになったうえで、「たったそれだけだから、もっと自分の子育てに自信を持って欲しい」と伝えています。
祖父母に甘やかされる日が5日あったとしても、それは子供にとっては日常ではなく、特別な5日間です。
360日/365日、ママやパパが日々積み重ねている子育ては、たった数日では揺るぎません。
そこはちょっとだけ大目に見て、祖父母の愛に包まれながら特別な時間が過ごせるよう、冷静に考えてみて欲しいなと思います。
だからといって、祖父母世代はたまにならどんなことをしてもいいというわけではありません。
「赤ちゃんの取扱説明書を作るのは、パパとママの仕事」だと、私たちは祖父母世代にいつも伝えています。
赤ちゃん自身が取扱説明書を持って生まれてきてくれればいいですが、残念ながら赤ちゃんは何も持たずに生まれてきます。
まだ今は真っ新なノートかもしれませんが、パパやママがちゃんと、その子だけの取扱説明書を書き足していってくれます。
祖父母は、我が息子や娘の取扱説明書こそ持っていますが、もう埃をかぶってしまっていて、ボロボロです。
それをぜひ孫にも…というのは、ちょっと違いますよね。
祖父母のみなさんには、パパやママが作成中の取扱説明書を隣で見せてもらいながら、大切な命を一緒に育んでいってほしいです。
家族みんなで、そうして子育て・孫育てをしていけたらとても理想ですよね。

***
孫育ては、世代間の違いを理解し、お互いを尊重しながら行うもの。
祖父母世代は「サポーター」として、パパママの育児方針を大切にしつつ、長年の経験をそっと活かすことで、子どもたちはより安心できる環境で成長していきます。
過度に距離を取る必要はありませんし、逆に頼りすぎない心がけも大切ですね。
家族みんなが笑顔で、心地よく支え合い、地域とも一体となって、温かい子育て・孫育てができたら理想です。
次回はいよいよ最終回。「孫育て10か条」についてのお話をお聞きします。
前回の記事はこちら↓
子育てと孫育て vol.1「祖父母世代のギャップと向き合うには?」
ライター 後藤麻衣子